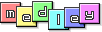双花 大学生

*LOVE FLIES*
すれ違い電車が背後の窓を騒がしく揺すり、思わず楸瑛は目を開けた。
眠っていたわけではないけれど、殆ど何も考えずに目を瞑っていた。
考えることを止めていたと言った方が正しいかもしれない。
会えるはずもないのに、彼の住む街の駅まで行って、改札を出ることも無く、折り返しの電車に乗った。
自宅の最寄り駅は既に過ぎ、それでも何となく各駅停車に揺られている。
このまま10分ほどで繁華街のターミナル駅に着く。
そのままアーケード街で女の子たちとその場限りの戯れの時間を持とうと思っていたはずなのに、気付けばとある駅のホームに立っていた。
6年間、通い慣れた坂道が見える。
中学・高校と同級生たちとふざけ合いながら、上り下りした道だ。
スーパーの前を通り、銀行街を抜けて、住宅街の中をひたすら上っていく道は、鍛えた楸瑛にも夏場などは堪えたものだが、
それでも、振り返れば広がる、港街の景色は好きだった。
身に付いた習慣で、意識もせずにこの駅に降り立ってしまったらしい。
そのことに楸瑛は苦笑した。
折角だからと改札を出る。
3年ぶりの懐かしい駅は、殆ど姿を変えていなくて、
ただCDショップに張り出された新譜の案内だけが、時の流れを告げている。
改札前の書店の入口に平積みされた文庫本を一つ手に取り、会計を済ませると、
少し迷ってから、奥まったカフェに足を踏み入れる。
30歳を少し過ぎた位と思われる女性のウェイトレスは、
彼がこの駅の利用していたころから変わらず、何処か少女めいた面持ちをしている。
以前のように女性用の笑みを浮かべ、一人と告げると、一番奥の楸瑛のお気に入りの席に案内される。
アイスコーヒーを注文して、先ほど買った本を開いてみる。
視線は紙の上を滑るけれど、内容など頭に入って来ない。
仕方なく、それとはなしに周囲の客を観察してみる。
彼が学生時代によく利用していたのは、イートインスペースのある向かいのパン屋だった。
そちらの方が値段的に手ごろだったから、同級生たちはそれを好んだのだった。
楸瑛がこの店に入るときは、大抵近くの大学の女子学生と一緒だった。
今も相変わらず、この店は女子学生で溢れている。
昔はその言葉の一つ一つが鳥の囀りのようも、美しい音楽のようにも聞こえた筈なのに、
今はただ、雑音だった。
グラスをテーブルに置くときのガタンという音も、
口に運ぶまでにフォークから零れ落ちるケーキも、
全てが見苦しいと、楸瑛は思った。
絳攸は、箸でもスプーンでも、とにかく綺麗に使う。
養子という立場上、養父母に恥をかかせまいと、あらゆる事で完璧であることを自分に課している。
楸瑛は、絳攸の箸使いが好きでもあり、同時に嫌いでもあった。
美しく、惚れ惚れするようだけれど、その背後にある養父の存在を、否応なく感じさせられるから。
1か月前、絳攸は唐突に楸瑛に言ったのだった。
「明後日から、黎深さまと一緒にアメリカに行く」と。
突然の話に楸瑛は理解ができないままに「そう。帰りは?」と聞いたのだった。
帰ってきた答えは、「解らない」
養父の気まぐれは、お前も知っているだろうと言われれば、頷く以外できることはなかった。
そして、これからフライトだ、落ち着いたら連絡するというメールを最後に、絳攸からの連絡は途絶えた。
黎深が傍にいることを思うと、楸瑛から連絡することは気が引けた。
黎深が自分の事を快く思っていないことは明らかだ。
下手に連絡することで、今後の連絡の術を断ち切られることだけは避けたかった。
楸瑛はもう一度文庫本を開いてみたけれど、やはり文字の上を視線が滑って行くだけ。
嘆息し、本を閉じる。そして腕を組んで、瞳を閉じた。
3年前までなら鮮やかに見えた景色が、今は何もかも色褪せて見せる。
恋をすると、世界が色づくというけれど、そんなのは嘘だと思った。
今自分に色づいて見えるのは、絳攸だけ。
降る様な桜も、キャンパスで揺れる緑も、燃えるように色づく山並みも、冬の朝にしか見えない遠くの島々も、
みんな、絳攸と見るから美しかった。
一人で見れば、却って空しさが増すだけ。
まさか自分が恋におぼれるなど、思ってもみなかった。
今までの戯れの関係は、いつも主導権は自分にあったから。
それが、今はどうだ。
ただのひと月連絡が無いだけで、自分はこんなにもぼろぼろで。
けれど、それでも彼という存在を知る前に戻りたいなどと露ほども思っていないのだ。
店のガラスの向こうを、見慣れた制服の男子学生が笑いながら通り過ぎる。
それを見ながら、まるで、過去の自分に笑われているようだと思い、楸瑛はもう一度ため息をついた。
楸瑛が自宅に帰りついたのは、夜の帳が下りきった頃だった。
駅前に最近できたショッピングモールの混雑は、ようやく落ち着きを見せてきて、
今日の様な平日だと、ホームの混雑も辟易するほどではない。
オートロックの解除ナンバーを押して、集合ポストの受取口へ向かう。
入っていたのは差出人も無い、一通のはがき。
表面に、『AIR MAIL』の文字。
あわてて裏返すと、ただ一言。
「連絡しろ、馬鹿!」
そして、隅には小さな文字で、こっちからかけても繋がらないのはわざとか?と。
楸瑛はあわてて携帯電話を確かめる。
昔のツケと言われれば仕方ないが、
楸瑛の携帯電話には、過去に顔を合わせた女性からの電話もメールも大量に寄せられる。
以前はその中から戯れの時間を過ごす相手を選んでいたものだ。
けれど、絳攸と出会って以来、そんな女性たちが面倒になり、携帯電話の設定を、登録以外拒否に変えたのだった。
そして、その設定だと、海外からの連絡は、全て拒否するようになっていたらしい。
空しさと、おかしさと、嬉しさが入り混じっておかしな気分だ。
目の奥がじんとするのは、今日何度も開いては閉じた文庫本のせいに違いない。
楸瑛は時計を見る。
あちらは、まだ明け方だ。
もう二時間だけ、我慢しよう。
それまでは、このはがきを眺めているのも悪くない。
そう思いながら、彼の書いた宛名の、自分の名前をそっと撫でた。
そしてそっと呟く。
やはり、色づいて見えるのはキミだけ。

私の初双花です。
楸瑛さんが乙女になってしまいました。
私のお世話になっているネイルサロンは、某私鉄のR駅にあるのですけれど。
その駅は、私と某さまの中で、楸瑛さんが高校時代に使っていた駅に認定されております。
その駅のカフェで妄想爆発させて書いたお話です。
2010/6/15 日記掲載SSを2010/7/10サイトに格納