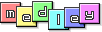埋み火
一目見て、魅了された。
その瞳の奥に秘められたしなやかな強さに。
その所作の一つ一つに現れる本物の美しさに。
そして振り向きざまに見せる、あどけない笑顔に。
彼女なら、出来ると思った。
その手を引いてやれるのは、自分だと思った。
否、本当は、自分以外の人間が彼女の手を引く事など許せないと思っただけ。
だから言ったのだ。
必ず、一番になろうと。
そのためには厳しくするけれど。
いつか二人で一番の高みに上ろうと。
彼女の瞳が自分を見つめたままで時が止まる。
さわさわと、風が枝を揺らす音がやけに大きく耳に響いて。
その割りに、隣のグラウンドで練習している野球部の掛け声は酷く遠く聞こえた。
やがて彼女が無言で頷く。
それを合図に、世界は再び動き始めた。
* * *
ベッドの上に広がった、艶やかな黒い髪。
しなやかなその髪に僅かに残る癖が、先ほどまでのパーティーで纏められていた髪が自由を得たばかりと物語っている。
気だるげに横たわる華奢な肢体を覆うのは、繊細な黒いチュールレースを幾重にも重ねたドレス。
はだけた裾からは、細く、しかし女性らしい曲線を描いた脚が伸びている。
その張りのある腿までを覆うガーターストッキングのレースから僅かに覗く肌の、透き通るような白さ。
あまりに僅かなその白が、ドレスを剥(は)ぎ取って、もっとその白を堪能したいという男の本能を刺激する。
顔に目をやれば、いつもの秀麗の優しく意志の強いそれとは違って、とろりと潤んでいる。
絳攸は大きく息を吐いて、ページをめくった。
今度は先ほどのベッドの上でシーツだけを身にまとい、物憂げに振り向く秀麗の姿。
メイクは先ほどよりもさらに薄く、しかしその唇だけは、上から塗ったのではない、内側から発色するような艶めきを放っている。
そこにいるのは溜め息が出るほどに美しく、そして妖艶な、大人の女。
絳攸が胸の奥で燻っていた火種が、ぱちぱちと音を立てて大きくなり、頭がくらくらとする。
その思いを振り払う様に、乱暴に雑誌を閉じる。
思った以上に大きく、ばさりと無粋な音がした。
「おやおや、まだ、ご機嫌斜めの様ですね」
いつの間に後ろに立っていたのか、社長の楊修が絳攸に声をかける。
「……楊修様」
隠していた失敗を見つかった子どもの様な気持と、この状況を作り出した楊修に対する不満とが絳攸の心の中で絡みあって、一瞬どんな表情をすればいいのか解らなくなる。
今の自分はきっと、とんでもなく情けない顔をしているに違いない、と絳攸は思った。
しかし楊修はそのことには触れず、眼鏡の位置を直しながら呆れたように言う。
「会社では社長と呼びなさい。いつもそう言っているでしょう」

第二話
絳攸にとって楊修は、学生時代からの先輩である。
高校の生徒会で出会い、そのまま大学・職場とずっと彼の後ろを歩いてきた。
前の会社で、芸能界のイロハを叩き込んでくれたのも、楊修だ。
彼が独立するときに、一緒に来ないかと誘われた時は本当に嬉しかった。
彼に認められ、彼の力になれるということが幸せだった。
今だって彼の事は、尊敬している。
しかし。
今回だけは、彼のやり方に素直に賛成できない自分がいる。
元はと言えば、自分が悪いということなど、百も承知だけれど。
不満が顔に現れていくのを隠そうとする気持ちなど、今の絳攸は持ち合わせていなかった。
しかし、楊修はそんなことなど気にもしない様子で、続ける。
「その号、完売したと出版社から連絡がありました。
その写真を見ていくつか映画の話も来ています。
今までとは少し違う役どころで、かつ重要な役が多い。
彼女にとってはいい転機になった。
君もこれから忙しくなりますよ。
全く、あの朝はどうしてくれようかと思いましたが、結果的には良い方に転んでくれて助かりました」
* * *
初めての水着グラビア撮影の日。
カメラを担当するのは、人気実力ともにナンバーワンと言っていい、女流フォトグラファー碧歌梨。
掲載雑誌も、業界ナンバーワンの超一流誌。
条件は完璧だった。
けれど、秀麗にはあの日、水着になれない事情があった。
その事情は、絳攸のせいなのだけれど。
その朝目覚めた絳攸は、頭痛と戦っていた。
頭痛の理由の半分は、酷い二日酔い。
そうしてもう半分の理由は、目覚めた時腕の中にいた女性だ。
最初は夢の続きかと思った。
だって秀麗が自分の腕の中で眠る筈など無いのだから。
けれど、頬をつねってみても確かに痛みは感じるし、何よりも腕の中の温もりが、現実の事と知らしめる。
そっと起き上って、まだ小さな寝息を立てている彼女を観察する。
秀麗の透ける様な白い肌に、ひとひらの赤い花びら。
無垢な彼女のイメージには、到底似合わない物。
いつもの半分も機能しない頭を何とか回転させて、記憶をたどり寄せる。
何度も反対したのに決まってしまった、秀麗の水着グラビア撮影。
その前日に、とてつもなく苛々して、いつもは飲まない酒を飲んだ。
そのまま秀麗に会いたくなって、ここに来て、それから……。
血の気が引いていくのを感じる。
そうだ。
ここに来て、秀麗が水着の試着をしていると言ったから、その姿が見たくてせがんだ。
実際に目にしたら、
恥じらいながら見せるその顔が愛おしく、
白く滑らかな肌が匂い立つようで、
この姿が雑誌に載って沢山の男の目に触れるなんて絶対に我慢ならないと思った。
だから、撮影なんてどうにでもなれ、そんな思いで、自分だけの印をつけたのだ。

第三話
酔っていたとはいえ、とんでもないことをしてしまった。
碧歌梨と出版社の顔を潰す事になれば、
それはそのまま秀麗の女優生命にかかわる事態だ。
秀麗は何時も、マネージャーの自分を信じ、
二人三脚で頑張るのだと言ってくれている。
それなのに、自分はなんということをしてしまったのだろう。
頭を抱える絳攸を叱咤し、タクシーを呼んで現場まで引っ張っていったのは
当の秀麗だった。
秀麗は一人碧歌梨に事情を話し、謝罪しに行った。
そして、何とか撮影できないかと碧歌梨に頼み込んだ。
その結果、当初予定していた水着のグラビアから設定を変更し、
“大人の紅秀麗”をテーマに撮影が行われることになった。
パーティーで出会い、一瞬で恋に落ちた二人が、
喧騒を抜け出して一夜愛を交わす、そんなストーリー。
女優としても、こういったグラビア撮影でも、
清純なイメージを守ってきた秀麗にとっては、突然の変更。
しかも普段と正反対の仕事内容に対応するのは、容易ではなかった筈。
けれど、秀麗は見事に演じ切った。
衣装に袖を通した時には不安に満ちていた顔が、
カメラの前に出るや否や、豹変する。
熱く、切なげな視線をカメラに向ける秀麗。
まるで、そこにいる男に、身を焦がすほどの恋をしている様に。
そして、その男に誘いをかける様に。
撮影を見守っていた絳攸は、
自分がどんどん不機嫌になっていくのを感じていた。
いる筈のない、秀麗の視線の先の男が憎くて仕方ない。
その視線が、自分に向けられたものでないことが堪らなく苦しい。
「予想外に化けましたね。灰吹きから竜が上りましたか。
まぁ、彼女の幅が広がって稼いでくれるようになれば、
私としては、文句はない。
だから今回だけは、見逃してあげましょう。
……ですが、次はありません。わかっていますね」
絳攸にそう告げる楊修の目は、
薄暗いスタジオの中、ライトを反射する眼鏡のせいで見えず、
絳攸には彼の心が読めない。
けれど、その口ぶりからは、
絳攸の心も、そして絳攸が昨日しでかしたことも、
全て見透かされている様に感じる。
だから、その時は何の反論もできなかった。
* * *
けれど。
「秀麗は、もう少し、今のままでも、良いのではないですか?」
自分の行動が引き起こした結果と思えば、
何とか今まで通りに出来ないかと思っての言葉。
しかし、楊修が眼鏡に手を遣りながら告げた言葉は、
絳攸にとっては予想外のものだった。
「紅秀麗は、全ての仕事を受けると承諾しましたよ」
「へ?」
咄嗟には言われた意味がわからずに、間抜けな返事しか出てこない。
「だから、紅秀麗は、これを機に自分の幅を広げることを受け入れた。
解っていると思いますが、この件に関しては私は無理強いはしていませんよ。
全ては紅秀麗が自ら選んだ道。
君がそれをサポートできないというならば、
彼女には他のマネージャーをつけることになります」
どうしますか? そう、目で問われる。

第四話
彼女のマネージャーを外れるなんて、考えられない。
けれど、これからも、あの撮影の時の様に苦しい思いをする事も考えたくない。
返答に窮した絳攸を見て、楊修は溜息をつく。
「まぁいいでしょう。君が答えを出すまでは、彼女は私が預かります。君はしばらく休暇を取って考えるといい」
「そんな、楊修様……」
「社長と呼びなさい。……解らないのですか?
マネージャーの心が揺らいでいれば、その心はタレントに伝播する。
結論を出さないままにだらだらと君が傍にいることは、紅秀麗の足を引っ張ることだと言っているのです」
話は以上と言って、楊修は出ていく。
残された絳攸はもう一度雑誌を開き、大きく息を吐き出した。
* * *
深夜、着信音に気付いた絳攸は携帯電話を手に取り、メールを開く。
差出人は、秀麗。
「今からお話しできませんか?」
たったそれだけの、簡単な文面。
けれど、まだ結論の出ていない絳攸を動揺させるには充分な内容。
絳攸は一度目を瞑り、深く息を吐き出した後に、短く返信する。
「こんな時間に出歩くな。明日も早いんだろう?早く寝ろ」
こんなものは言い訳だ。
自分自身が一番理解しているけれど、今、秀麗に会ったら、自分はどうなってしまうか分からない。
そもそもが、自分が播いた種で、それを秀麗が、補って余りある物へと昇華した。
その仕事ぶりに不満を持つだなんて、許される訳がない。
それでも、心の中に燻ったこの火種を、持て余している自分が居る。
この火種を持ったままで秀麗に会ってはいけない、そう感じた。
それなのに。
再び鳴り出した携帯電話。
今度は、電話の着信音。
表示窓には、秀麗の文字。
息を整えて、着話ボタンを押す。
それまでの時間は、おそらく3コールか4コール、その程度のもの。
けれど、絳攸には随分とゆっくり時間が流れていくように感じた。
「……秀麗、どうした?」
流石に白々しいかと思いながらも、こちらからはまだ話せる事が無いと、心の中で言い訳する。
「実は、もうマンションの下まで来ているんです。どうしても、今日お話ししたくて」
「……こんな遅い時間に、一人で男の家を訪ねるなんて、無用心が過ぎる。今日は、帰れ」
「ずるいです。
絳攸さんが私の家に来るのはよくって、私が絳攸さんを訪ねるのは駄目だなんて、
そんなの筋が通りません。
お話できるまで、私は帰りませんから」
元来彼女は、言い出したら聞かない、そんな所を持っている。
仕事に関して自分の意志を貫き通す、その姿は好ましいと思っていたけれど。
「……秀麗、頼む、困られないでくれ」
「絳攸さんこそ、困らせないでください。私はただ、話を聞いて欲しいだけです。話を聞いて下さったら、帰りますから」
その声は、彼女特有の真っ直ぐさとそして、いつもは見せない不安とが入り混じったもの。
絳攸はひとつ息を吐き、そうして自室まで上がってくるようにと告げて電話を切った。

第五話
秀麗がこの部屋にやってくるまで、おそらく後五分ほど。
それまでに、少しでも頭の中を整理しておかねばと思うのに、
こんな時に限って考える事を心が拒否する。
かわりに心に浮かぶのは、あの撮影の日、
カメラに向けて秀麗が見せた蠱惑的な眼差しばかり。
結局、何の結論も出せないままに時間だけが過ぎ、
無常にもインターホンが秀麗の来訪を告げる。
ドアを開け招き入れた秀麗は、
三和土(たたき)に立ち尽くし、じっと絳攸を見つめる。
その顔は、抑えてはいるけれど心のでは怒っている時の表情だと絳攸は知っている。
そしておそらくは、自分も同じような表情をしているのであろう。
二人の間を気まずい沈黙が流れる。
「……、秀麗、とりあえず中に入れ」
気まずさに耐え切れず、絳攸が先に口を開く。
しかし秀麗は、ここで良いと首を横に振る。
そしてぽつりと呟くように言う。
「明日から、私のマネージャーは、楊社長と聞きました」
解っていた事だけれど、
彼女の口から改めて告げられれば、それだけで、
当たり前のように彼女の隣にいる事のできた昨日までの日々が、
もう当たり前ではなくなるのだと、その残酷な事実に向き合わされる。
「あのグラビアの評判が、かなり良かったらしくてな。
社長もこれを機会にお前をもう一段階引き上げようと、そういうことだろう」
これは秀麗の聞きたい答えではない。
しかし、嘘でもない。
ずるい答え方をしたと自分でも解った。
しかし、秀麗はただ、首を横に振って悲しそうに呟く。
「……どうして?」
「秀麗……」
「どうして、そんな言葉で誤魔化そうとするのですか?
私が絳攸さんに相談も無く映画の仕事を受けた事を怒ってらっしゃるのですか?」
「怒ってなんか……」
「嘘です!
そうじゃないなら、どうして私のマネージャーでいてくれないんですか?
私がタレントとして至らないからですか?
それとも他のタレントにつきたいからですか?」
「秀麗、そうじゃない……」
「私は、声を掛けてくださったのが絳攸さんだから、信じてこの世界に入りました。
一番の女優と、一番のマネージャーになるって言う約束は、嘘だったんですか?」
漆黒の瞳から、ぽろぽろと雫が滴り落ちる。
その姿すらも、美しい。
いつの間にこんなに美しくなってしまったのだろう?
気付いたときにはその小さな体を腕の中にぎゅっと抱きしめていた。
「悪かった」
「こう、ゆう、さん……?」
背中にただ流しただけの絹糸のような黒髪を撫ぜながら、絳攸は秀麗に告げる。
「お前ばかりが急に羽化したように綺麗になってしまって、
俺だけが置いていかれたような気持ちになって居たんだ。
だけど、それなら俺がお前に追いつくように走れば良かった。
それだけの事だったんだな。」

「……私が、絳攸さんを置いて行く?」
「あぁ、この前の撮影は、
カメラの前でのお前の変身ぶりに見ているだけで、鳥肌が立つほどだった」
「あ、あれは、あの撮影が上手くいかなかったら、
今まで絳攸さんと築いてきたキャリアが全部振り出しになると思って必死で……」
「だけど、あの場の誰が期待していたものよりも、
ずっと上をお前が行っていたことは本当だ。
本来ならあの場で一番に誉めてやらなければいけなかったのに、悪かったな」
「いいえ。絳攸さんは私を誉めては駄目です。
誉めてくださるのは、私が一番の女優になったときまでとっておいてください」
「じゃあ、早く一番になってくれ」
「絳攸さんが一緒なら」
「あぁ、もちろんだ。
だけど、一番になるためなら、手段は選んでいられないぞ。今まで以上に厳しくする」
「ふふ、望むところです」
そういいながら秀麗が顔を上げたから、二人の視線がぶつかって、
そしてその瞳と瞳の距離感に二人ともが驚き、弾かれるようにして離れる。
「す、すみません。泣いたりなんかするつもりじゃなかったんですけど」
「い、いや、俺のほうこそ悪かった」
急に体温が上がったようになって、
鼓動もやけに高鳴って、とにかく絳攸は落ち着かない。
「そ、そうだ秀麗。明日の仕事は早いのか?」
「いえ、明日は、オフなんです」
「そうか。……そういえば、どうして俺の家がわかったんだ?」
秀麗がここにくるのは初めての筈、そう思い問う。
「あの、楊社長に聞いて……。
すみません、いきなりご迷惑でしたよね」
「いや、それは良いんだが……」
結局自分は楊修に全て見透かされ、
彼の手のひらの上で踊らされていただけという事か。
そう思うと情けない気持ちと、
少しだけの感謝の気持ちが生まれてくる。
いつか、秀麗と二人、
楊修も文句をつけられないほどの存在になってやる。
我知らず表情を厳しくした絳攸に、秀麗が心配そうに声を掛ける。
「絳攸さん、やっぱり、怒ってらっしゃいますか?」
「いや、違うんだ。秀麗、一緒に頑張ろうな」
絳攸の言葉に返事をする代わりに頷いた秀麗の笑顔は、花のように美しかった。
* * *
同じ頃。
事務所の社長室で一人腕を組み、眼下に広がる街を見ながら楊修は呟いた。
「女優にとっては恋は糧ともなるもの。
けれど、溺れるのはいただけません。
絳攸、解っているでしょうね」
窓に映った彼の顔は、言葉に反してほんの少しだけ嬉しそうだった。
【了】

あとがきという名の、言い訳
ブログSSに書いていた芸能パロの続き、書いてしまいました。
楊修様のたくらみはまだまだ続きそうなので、
折を見て続編も書くかもしれません。
全くどうでもいいことながら
秀麗ちゃんのグラビアシーンを書くのに
ぐー○るでグラビアを検索しまくった女とは私の事です。
可愛いお姉さんは好きです。
2010/07/18