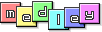「……そ、そんなに見られたら……」
それだけ言うと、カノジョは丸い大きな目を伏せて、俯いてしまった。
解ってない。
本当に、解ってない。
だってそうだろ?
実家の八百屋で毎日重い野菜を運び、
小さな体に似合わないギターを背負って歩いているせいで、
カノジョの腕は多少筋肉がついてはいるけれど、
タンクトップからすらりと伸びた腕はどう見たって男のソレとは違う。
襟元に覗く鎖骨も、スプーンを握る小さな手だって、
みんなみんなカノジョが確かに自分と違う「女の子」だって事を示してる。
もうそれを見ているだけだって、僕は自制心を総動員しているわけだけど、
無邪気な顔をしてまるで煽る様に、カノジョは言うんだ。
「……そんなに、見ちゃ、イヤ、です」
耳まで真っ赤に染めて、ふるふると肩を震わせて、絞り出すようにそんなことを言ったって、
僕の心に宿った火を大きくするだけだってこと、まだカノジョは気付いてない。
本当はもう、僕の自制心は用をなしていなくて、
ただ、目の前にいるこの愛しくて憎らしいイキモノをどうやって捕まえるか、
その過程をシミュレーションしているわけだけど。
カノジョにとって、僕はオトナのオトコだから、精一杯カッコつけなきゃいけない。
そんなサディスティックな気持ちの裏側で、僕の心はひどく幸せな音に包まれていく。
カノジョは知らない。
男がどんな目で女の子を、自分の恋人を見るかなんて。
カノジョは知らない。
そんな欲望とは無縁に、
ただただ無垢なままで過ごしてきた彼女の日々に終止符を打つ男が僕だって事だけで、
どんなに僕が満たされるかを。
「なんで、嫌なの?」
「なんでって、だって……」
言わなくたって解るでしょ?って今にも泣き出しそうな真っ赤な目で訴えられたって、
今更そんなもので僕の欲求が満たされるはずもない。
でも、焦ってはダメ。
この犯罪的に可愛いイキモノには、ゆっくりと時間をかけて教えてあげなければ。
その姿が、いかに男を誘うかを。
キミはもう僕のものなんだから、そんな姿を見せていいのは僕の前だけだって事も。
「なんで嫌なの? 理由を言ってよ」
カノジョの姿を見ると、可愛すぎて正直頬が緩んでしまうから、
視線を合わさないままにして、僕は言う。
そうすると僕が不機嫌になったと思って、カノジョの瞳はたちまち不安と恐怖で満たされる。
そう、だからそういうところが、犯罪的に可愛いいんだってこと、
そろそろ自覚してくれないと本当に、困る。
それなのにカノジョは、「困らせないで」って縋る様な目で僕を見るんだ。
もうそろそろ僕の我慢も限界で、演技じゃなく不機嫌な声が出る。
「なんで嫌なの? 理由を言えよ」
僕の声を聞いたカノジョの肩はびくんと大きく震えて、
それから本当に小さく、絞り出すような声でカノジョは言った。
「だって、恥ずかしい、デス」
たったそれだけいうと、もうこれ以上は無理というほどに頬を染めて、俯いて。
「でも、僕は見てたい」
それは嘘。
本当はもう見ているだけなんかじゃ足りない。
音の漏れないこの部屋の中に閉じ込めて、僕だけの声を聞かせてほしい。
だけど、今は、まだ何も知らないカノジョのために、もう少しだけ時間をあげる。
「でもさ、どうしても見ないでって言うなら、そうしてもいいよ」
そう言ってやるだけで、カノジョの顔には満面の笑み。
汚れを知らぬ、無垢な笑顔。
罠にかかったことに気付かぬままに、カノジョは申し訳なさそうに
「ワガママ言って、ごめんなさい」って言った。
その様子はやっぱり犯罪的に可愛い。
まぁこれは僕が彼女に溺れているってことなんだろうけど。
だけどさ、他の男がカノジョに溺れないでいてくれた奇跡がこれからも続くと信じるほどには、僕は楽観的じゃない。
だから、知ってほしいんだ。
僕がどんなにキミを好きかを。
僕がもうキミを離す気が無いってことも。
だから僕は言う。
「見ないかわりにさ、ちょっとだけ味見させてよ」
カノジョの手元のアイスクリームは、もうすっかり融けてしまってどろどろで。
それを見たカノジョは困ったように、こっちを向いた。
「えっと、融けちゃいました。今度、おんなじの、買ってきますね。っていうか、今! 今買ってきます!!」
どうやらカノジョは、僕が本当にアイスクリームの味が気になって不機嫌になったと思っているらしい。
カバンの中から財布を取り出し、スカートの裾を揺らして、出ていこうとする彼女を捕まえる。
「買ってこなくていい」
「でも……」
「味ならこうすればわかるから」
そう言って、カノジョの小さな唇を塞ぐ。
一体どうやったら、こんな小さな体で、あんな歌を歌えるんだってほど細い体躯を、抱きしめる。
吐息がかかるほどの距離だけ離れて、僕は言う。
「口唇、開いて。あと、息止めないで」
それだけ言うと、返事も待たずにもう一度カノジョを味わう。
最初はガチガチだったその背中を、何度かゆっくりと撫でると、
不意にすとんと力が抜けて、かわりに崩れ落ちそうになるのを抱きとめる。
角度を変えながらもけして離れることのない二つの口唇の間を、
カノジョの小さな声が、最期の抵抗を試みる。
「キスは、……一日、……一回って」
だからもうダメと逃げようとするけれど、そんなこと許さない。
「でもこれは味見だから、今日の分のキスはまた後でね」
そう言うと僕は、もう抵抗できないように、カノジョを味わった。
ねぇ、キミは最高の楽器。
キミの声を聞くだけで、いくらだって歌が生まれてくる。
でも、その歌を歌うキミを誰にも聞かせたくないって思うのは僕の我儘かな?
それに僕はまだ、キミの声の全部を知っているわけじゃない。
でもその声を聞くのが僕だけだってことは、決定事項。
だから、あと少しだけ待ってあげる。
その間に解ってよ、僕がどんなにリコに夢中かってこと。
【了】

あとがき、という名の言い訳
カ/ノ/嘘のアキくんとリコちゃんのお話です。
ツイッターで流したものを再掲させていただきました。
原作はマンガなのですが、まだまだ明かされていない事が沢山ありそうで、
毎回転がり回りながら読んでいます。
彩/雲/国以外のお話を書いたのは初めてです。
ワタシもカ/ノ/嘘を愛し過ぎているので、もっと書きたいのですが、
二次でつけいる隙のないほど原作が素晴らしすぎるのです。
今回はヒーローのアキくんとその彼女のリコちゃんで書かせていただきましたが、
まだまだ好きなキャラクターはいるのでまた折を見て、書けたら良いなぁと思っております。
2010/09/30 小鈴