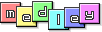ゆっくりと、静かに。
黒塗りの自動車は、林の中を進んでいく。
その後部座席には、ひと組の男女。
かたや、燕尾服を着こんだ洒落者の美青年。
その隣には、この美青年の隣を飾るにふさわしい、美女。
但し、彼女が仏頂面でなければ、の話であるが。
そう、青年こと、陸軍参謀本部作戦課所属、藍楸瑛の隣には、豪奢なドレスの美女。
癖一つないぬばたまの長い髪は、腰のあたりまでさらりとただ流され、
眉のあたりで揃えられた前髪が、その美しい顔と意志の強い瞳を効果的にひきたてている、筈である。
何故断定形でないかと言えば、それは、現在彼が見ることを許されているのは、彼女の後頭部だけだからである。
しかし薄暗くなり始めた窓の外のおかげで、僅かにガラスに映り込んだ彼女の瞳と目があった。
「だらしない顔をするな。元の顔だちは仕方ないとして、いつものもう少し取り澄ました顔はどうした?」
左肘を、ドアに付き、その白い腕の先に形の良い顎を載せながら、絳攸はひどく不機嫌そうな声を出す。
「そんなに怒らないでよ、絳攸。綺麗な姿が台無しじゃないか」
絳攸とは対照的にのんびりとした口調で楸瑛は答える。
その口調に痺れを切らしたように、絳攸はぱっと楸瑛を振り返る。
長い髪がふわりと浮いて、宙を舞い、すとんと元通りに収まる。
「怒らないでいられるかっ! 何で私が、夜会になど出ねばいけないんだ? しかも、女装で!!」
もう、今日何度目かになる問いを、絳攸は楸瑛に投げかけた。
類稀なる優秀な頭脳を持つ彼女の事、一度の説明で理解ができなかったはずがない。
にもかかわらず、何度と無く同じ問いを繰り返すのは、
彼女が現在置かれた状況に対して抱いている不満の表れ以外の何物でもない。
しかし、この藍楸瑛と言う男、状況を楽しむことと、楽観的に考えること、
そして火に油を注ぐことが得意な人間であった。
故に、彼が敢えて選んだ答えは、彼女の望んだものなどでは決してなかった。
「絳攸、女の子がドレスを着て着飾る事は、女装とは言わないよ?」
もしここが、参謀本部の彼女のデスクであったなら、
手の届く範囲で一番分厚く重い資料が即座に飛んで来るであろう発言だ。
しかしながら、この車内には、彼女が武器とするに適当な書類など、あるはずも無かった。
唯一彼女の手元にある小さなバッグだけは
投げようと思えば投げる事は可能であるが、彼女がそれを実行に移すことはない。
何故ならば、それは彼女の敬愛する母からの借り物であるからだ。
更に言うと、その華奢なバッグには、化粧直し用の紅のほかに、
その外見にはとても似合わないブローニングなども入れられている。
不満は隠そうともしないものの、それが任務である限りにおいて、
彼女はその遂行に全力を尽くすし、またその几帳面な性格から、火器類を乱暴に扱うことは無い。
そう言った訳で、絳攸は投擲の代わりに、厳しい視線で楸瑛を一瞥すると、
再び無言で窓の外へと向き直ってしまった。
楸瑛はゆっくりと、絳攸の背中を眺める。
元来、色白の印象の彼女だが、
大きく抉れたカッティングのドレスからのぞいた彼女の背中は、透き通るように白かった。
普段太陽にも、そして誰の目にも晒されることのない、汚れを知らぬ、白。
それはまるで淡雪のようで、
触れればそこからあっという間に融けて消えていきそうな危うさを含んでいる。
その白と、そして真っ直ぐな黒い髪が、彼女のまとうドレスの艶やかさをより一層引き立てている。
普段の絳攸を知る人が見たとしても、今の彼女が陸軍参謀本部作戦課の李絳攸とは気付くまい。
実際、楸瑛ですら、着替え終わった彼女を見た瞬間は、わが目を疑ったのだ。
高級住宅地として名高い地域の中でも、特に奥まって見晴らしがよく、
そして広大な敷地を持つ紅家別邸の豪奢な応接室で、
楸瑛が一人コーヒーを飲んでいたのはつい二時間ほど前の事。
ある理由から、仕方なく訪れた楸瑛であったが、
内心は、いつこの邸の主が帰還するかと、冷や冷やしていた。
この邸の主とは、華族・紅家の当代当主にして、
陸軍参謀本部作戦課の長である、紅黎深大佐だ。
楸瑛の家も、同じく華族の家柄である藍家であるのだが、
この当代当主である三つ子の兄と、黎深とは、士官学校時代の同期であり、
両者が顔を合わせれば必ずや諍いが起きることは、陸軍内でも有名な話であった。
そのせいもあって、黎深と顔を合わせるのは、楸瑛も気まずい。
幸い、この時間はまだ、黎深も作戦課の自室で仕事をしている
(体で参謀本部内を同期やら敬愛してやまない兄やらを探しまわっていることもまた、有名な話ではあるが)筈なので、
帰宅することは無いと思うが。
しかし、養女を溺愛する大佐がこの事を聞きつけて急ぎ帰宅するということも、十分に考えられる。
したがって、一刻も早く、この邸を出たいというのが、楸瑛の本音であった。
そっと、胸元にしまった時計を取り出し、時刻を確かめる。
この邸にやってきて、30分。
そろそろ、部屋の側に控えたメイドと適当な話をしながら待つことにも飽いてきた。
そんな時、黎深の妻であり、絳攸の養母にあたる百合が、ドアを開け、顔をのぞかせる。
「楸瑛君、お待たせ」
心なしか、声が弾んでいる。
本人と違い、この話に大変乗り気であった百合の事である。
普段は着飾る事に興味を示さない娘を相手に、ここぞとばかり腕をふるうのが楽しかったに違いない。
「急なお願いで申し訳ありませんでした」
そもそも今日楸瑛がこの場にいるのは、
楸瑛の属する参謀本部情報課の仕事に、絳攸も参加することになったため。
情報収集のため参加する夜会で、今夜は一つ大きな捕り物に発展する可能性があった。
普段は、付き合いのある貴族の令嬢を同伴する楸瑛であるが、
今夜ばかりは、部外者はなるべく少ないほうがいい。
そんなわけで、課は違えども同じ参謀本部作戦課に属し、
しかも参謀本部内で唯一の女性である絳攸に白羽の矢が立ったわけだ。
自分の上司がどうやって彼女の上司に相談し、承諾を取り付けたかは、楸瑛は考えたくもなかった。
どう転んでも、よからぬ取引があったに違いない。
そう思うと、改めて、百合に詫びる気持ちが強くなる。
「いいのよ~。私は楽しませてもらったし。
お仕事ばかりで心配していたけれど、今回ばかりはお仕事に感謝ね」
楸瑛の心の内を知ってか知らずか、百合はただにこにことして応える。
「あの、それで、絳攸は?」
「……着なれないから恥ずかしいみたい。
でも、母の欲目を差し引いても、いい出来だと思うわよ?」
そういうと百合は、空いたままになっている扉に向かって、出ていらっしゃい絳攸と呼びかけた。
しばしの沈黙の後、現れた絳攸を目にして、部屋の中は静寂に包まれる。
そこにいるのは、軍服姿で髪にも肌にも、
最低限の手入れしかしない、作戦課の将校ではない。
細く、無駄な肉のない身体は、しかしゆるやかな曲線で構成されていて、
それが男のものではないと証明している。
その肢体を覆うのは、深紅のドレス。
無駄な装飾など一切ない。
胸元からくるぶしまでを、身体に沿うように覆うだけ。
彼女の銀色の髪は、美しいけれど目立つから、
黒いストレートヘアの鬘で隠しているのだが、
その黒髪が、大きく開いた背中の白さを際立たせて、妖艶ですらある。
正直、絳攸とはけして短い付き合いではない楸瑛も、
彼女がこれほどに美しいと思ってみたことも無かった。
何か言葉を発しようと思うけれど、出るのはただ、感嘆のため息ばかり。
沈黙を破ったのは、絳攸であった。
「似合わないのは、私が一番分かっている」
そう言うと、そっぽを向いてしまった絳攸は、本当に言葉の通りに思っているらしい。
「こうゆうー! 可愛いって言ったじゃない。まだ信じてくれないの?」
養母の少し拗ねたように口ぶりに、絳攸は、少し慌てたように答える。
「あ、あの、百合さんが悪いんじゃなくて。
何て言うか、その、やっぱりこういう格好は、普段着慣れている者がするべきと言うか」
「普段から着てちょうだいってお願いしても、いつも絳攸は、着てくれないじゃないの!
お仕事に邪魔になったらいけないからと思って我慢しているけど、
本当は私も、絳攸のお休みの日には、一緒に着飾って出かけたり、お茶を飲んだりしたいのよ。
それなのに、お休みの日も、お仕事ばっかりで……」
「ゆ、百合さん、そんな……」
敬愛する養母を悲しませてしまったかと、絳攸は、おろおろと視線を彷徨わせ、
呆気にとられてただ見つめていただけの楸瑛と、視線が交わる。
それをどういう意味に捉えたのか、楸瑛は百合の手をとると、頬笑みを浮かべる。
「お義母様、ご安心ください。絳攸はとても美しいで……」
みなまで言い終わる前に、言葉が途切れたのは、絳攸の鉄拳が下されたからだ。
「百合さんに近づくな、この常春が」
「酷いよ、絳攸。君の美しさについて、義母上と語り合いたいだけなのに」
「馬鹿なことを言う暇があったら、出かけるぞ」
そうして、待たせていた参謀本部の車に乗り込んだ二人であった。
林の中、現れた洋館のポーチに車が滑り込む。
楸瑛はすぐに車を降り、反対側に回って、ドアを開け手を差し出す。
応える絳攸の顔には、完璧な微笑。
(全く、任務の事になると、切り替えが早いんだから)
楸瑛は苦笑するが、すぐに絳攸のハイヒールに踏みつけられる。
「任務の時間だ。集中しろ」
相変わらずの美しい笑顔で、しかしその言葉は完全に、陸軍将校のもの。
楸瑛も思わず、背筋を伸ばす。
エントランスに向かう階段を、絳攸の手をとり、上る。
「さあ戦いの始まりだ」
楸瑛の耳にだけ届く絳攸の言葉は、どこか嬉しげで、
不意に大佐の事を思い出して、楸瑛は我知らず一瞬眉を顰めるが、
今はそんな事を気にしている場合ではない。
楸瑛に手をひかれエントランスをくぐる絳攸の背中で、吹き始めた風に煽られた髪が揺れていた。
【続】