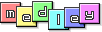「星に手を伸ばすようなものだ」
そう言ったのは、君だけど、
君はきっと覚えてなどいないだろうね。
だからせめて、私が覚えていることくらい、許しておくれ。
流星群
それは忘れもしない冬の出来事。
久々に飲み過ぎたようだと、楸瑛は思った。
自分のことではない。
自分以外の者がその座につくことなど、
有る筈も無いと信じて疑わなかった主席の座を
いとも鮮やかに奪ってみせた年下の友人のことである。
あと半月もすれば新年を迎える慌ただしい季節。
春に士官学校を卒業して以来、
それぞれが割り振られた部署での仕事に従事しているから、
全員が揃うのは久々だ。
二日ほど前から急激に厳しくなった寒さの中でも、
陸軍の訓練予定が変更される事は無かったから、
冷え切った体を温める為にと、強めの酒を飲んだのだ。
けれど、けして酒に強くないと自覚して、
酒量を抑える事には慣れている筈の絳攸が、
今日に限って歩けなくなるほどに杯を重ねたのは、
他に理由があってのことと知っている。
知っているからこそ、
車を帰してこうして自らの背に絳攸をおぶって歩いているのだ。
楸瑛が見つけたときには、
絳攸はロビーのソファに深く腰掛けていた。
その少し前、宴の席を抜けて行ったときには
化粧室にでも行ったのかと思ったのだが、
それにしては戻りが遅いから、
もしや戻れなくなっているのではないかと探しに来たのだ。
本人は認めたがらないけれど、
絳攸は迷うことにおいてもその才能をいかんなく発揮する。
そんな絳攸を、いち早く見つけてはさり気無く連れ戻すのは自らの役目と自負している楸瑛であった。
まして、今日の絳攸は何時もなら考えられない程に酒を飲んでいる。
いくら、軍服姿とはいえ、
妙齢の女性である絳攸を放っておく事など出来ないと、
自らもまたさりげなく輪を離れた楸瑛であった。
「絳攸、大丈夫かい?」
後ろから近づきながらかけた声に返事は無い。
よく見れば、細く伸びた腕に乗せられた頭は、小さく揺れている。
どうやら、連日の激務と酒のせいで、うたた寝をしてしまったらしい。
「こんなところで眠っては危ないよ――」
送っていくからと続ける筈だった言葉が途切れたのは、
彼女の頬に一滴流れ落ちるものを見てしまったから。
起こさない様にそっと指で拭ってやりながらも、
楸瑛は胃の腑が燃えるようになるのを感じた。
男ばかりの陸軍参謀本部で異例の出世を誇るのは、
養父の引き立てなどではなく、
彼女自身の努力と才能によるものだと楸瑛は知っている。
そして、好奇の目やくだらないやっかみなど相手にすらしない
芯の強さを持ったひとだという事も。
そんな彼女が、たとえ夢の中とはいえ涙を流す理由と言ったら、
それは彼女の上司が関係しているに決まっている。
絳攸の薄い色の瞳が見つめ続けるのは、昔からただ一人だけ。
養父である紅大佐だけをずっと追いかけている。
幼い頃、飢えと寒さで死にかけていた絳攸を拾い育てたのが紅大佐だ。
それはきっと、大佐にとってはいつもの気まぐれの一つでしかないのに。
もしかしたら、気まぐれだと分かっているからなのかもしれない。
絳攸は全てを大佐に差し出すのだ。
ただひたすらに、その笑みを、その掌を欲して。
おそらくは、今日聞かされた作戦が関係しているのだろうとは楸瑛にも想像がつく。
急に呼び出され、暫く作戦本部の仕事を離れると伝えられた。
与党の大物議員Sから内々に陸軍に依頼があったのだという。
楸瑛自身は、潜入のために参謀本部を離れるのは慣れたものだけれど、
今回は絳攸も一緒だという。
それが、紅大佐も了承したこととなれば、
絳攸の動揺も無理からぬことと楸瑛は思った。
絳攸にとっては、紅大佐は闇の中一筋差し込んだ光のようなもの。
ただ、その光を追いかけて陸軍に入り、必死に走ってきた絳攸にしてみれば、
参謀本部を離れる事は光を失うにも等しい。
解っているけれど。
思い出してまた深く吐いた息が白く曇って、
ガス灯に照らされながら散っていく。
立ち止って、それを何となく見送っていると、
背中に感じる温もりが僅かに動いた。
「絳攸、気がついた?」
「……なんで? というか、何だこれは! お、おろせ、馬鹿」
自分が楸瑛に背負われて、脚も晒しているとようやく気付いた絳攸が背中でばたばたと暴れる。
心の中にひどく残酷な心が広がっていくのを感じながら、楸瑛は言った。
「降りたければ、降りればいいさ。
だけど、君は一人では歩けないと思うし、歩けたとしてここから家まで帰るなんて無理だよね。
まあ、朝になれば大佐が探してくださるだろうけれど、この寒さだ。
いくら君でも命の保証はないと思うけどね」
大佐という単語を聞いた途端に、絳攸は大人しくなる。
その事がまた、余計に腹立たしい。
冬は、嫌いだ。
澄んだ空気は、感情までも隠さずに全てを透かせてしまうようで。
自らのうちにとぐろを巻いた浅ましい気持ちの存在を、否応なく突きつけられる。
普段のように軽口をたたく気にすらなれずに、楸瑛は黙って歩を進めた。
帝都とはいえ流石に深夜である。
出歩く人々の姿は無く、高級住宅街に、ただ楸瑛の長靴が地面を蹴る規則正しい音だけが響く。
不意に、耳元を吐息がかすめるのを感じた。
「なあ、……楸瑛」
少しだけ不安の滲んだ呼びかけを、無視することなど出来る筈も無かった。
「なんだい?」
「私は、酔っているのか?」
今更、所在無さげに問いかける絳攸に思わず笑いが零れる。
「ああ、多分ね」
「でも、お前も酔っているだろう?」
「まあ、君ほどではないけどね」
絳攸の意図する事は解らない。
けれど、ただ短い言葉のやり取りが、こんなにも暖かいのだと楸瑛は思った。
そんな楸瑛にお構いなしに、絳攸は言葉を続ける。
「お前も酔っていて、私も酔っている。この会話も明日には忘れてしまうよな」
是と答えてほしいのだと解ったから、ただ続きを促す。
「星に手を伸ばすみたいなんだ」
「うん」
「追いかけても追いかけても、絶対に届かないって解っている」
「うん」
「それでも、手を伸ばしてしまうんだ」
「うん」
焦がれるほどの思いで絳攸が追いかけるのは、気まぐれな大佐だけ。
大佐の言葉だけが、彼女の心に響く。
それは楸瑛にとっては酷く残酷な事実。
そして、自らにうちにもまた、ただ一人だけを希う思いがある事も解っている。
その思いを隠して、素知らぬ顔で彼女の側に立っている。
彼女の幸せだけを願ってやることなど到底できない。
けれど離れる事も出来ずに、偽りの笑顔で彼女の隣に立つのだ。
こんな思いを知ったら、彼女は酷く軽蔑するに違いない。
気付けば規則正しい寝息が背中から聞こえてくる。
温もりと冷たさの両方を感じながら、楸瑛はただ歩いた。
「へっくしゅん、――って絳攸酷いなぁ」
盛大なくしゃみをした楸瑛は、あからさまに距離をとった絳攸を笑う。
今日は久々に士官学校の同期の会合があった。
卒業して五年。
互いに忙しくなり、全員が顔をそろえる事も難しくなってきた。
それでも楸瑛が声をかければ、
なんとか顔だけでも出してくれるものが多いのは嬉しい事である。
最初の店を出てから、二軒ばかりはしごをしたあと、
酔い覚ましに少し歩こうと言ったのは絳攸だった。
それなのに、心配するどころか、
如何にも伝染してくれるなと言わんばかりの態度をとられれば、
多少むくれてみたくもなる。
「安心しろ。お前は馬鹿だから風邪をひく事は、無い。絶・対・に」
絳攸の言葉に抗議の視線を送ってみたものの、あっさりと切って捨てられて、
それでも楸瑛も食い下がる。
「ちょっと、いくらなんでも酷過ぎるよ。
それに、私が風邪をひかないなら離れる必要は無いじゃないか」
「馬鹿がうつったら困るからな」
「……はは、そう」
心の中にまで北風が吹きこんで来たようだと思いながら、
それ以上の反論をやめて、楸瑛は空を仰ぐ。
冬の澄んだ空気に、星空との距離が縮まったかのように錯覚し思わず足を止めると、
数歩先で絳攸も立ち止まる。
ただ無言で見上げた夜空に、一筋の光が走った。
そういえば、昨日あたりから流星群だと言っていたか。
降るような星の下、言葉も無く吸い込まれる様にして立ち尽くす。
瞬きながら流れる星は、手を伸ばせばこの掌の中にも舞い降りそうで思わず右の腕が動く。
けれど掴める筈も無く、当然のようにただ空を掻いただけで、
自らの滑稽さに笑いがこみ上げた。
その声にこちらを向き直った絳攸の目は不思議なものを見る目で、
その事に楸瑛は何故だか安堵してまた笑った。
触れられなくとも、側にいられるならそれでいい。
あの夜の絳攸は、雪のように儚く消えてしまいそうだった。
もちろん、次の朝には何事も無かったように士官の顔に戻っていたけれど、
それでも楸瑛は彼女の背中を見るたびに
そこに張りつめたものを感じずには居られなかった。
きみは怒っているほうがいい。
涙を流したきみは、自らの涙で溶けて消えてしまいそうだったから。
そんなことを言ったら、きみはもっと呆れた顔をするだろうけれど。
それでも思わずにはいられない。
きみは怒っているほうがいい。
怒っているきみは、確かにいのちの温もりを感じさせるから。
君のために星を掴まえるだなんて、大それたことを言うつもりはない。
だけど、星を見つめるきみの体が冷えてしまわない様に、
そのくらいなら私にも何かできると思うから。
だから、きみの側に立つことくらい許して欲しい。
星に手を伸ばすようだと言ったきみなら、この想いまで否定はしないでいてくれるだろう?
そんなことを考えていると不意に頬を掴まれて我に帰る。
「……こうゆう、いひゃいよ」
「楸瑛。お前の取り柄は顔くらいしかないんだから、情けない顔はするな。
何か悩みがあるなら聞いてやるくらいは、私にもできるから。
お前がそんな顔をするという事は、何か悩みでもあるんだろう?」
鈍い様で聡いのか、聡いようで鈍いのか、
絳攸はどちらに当てはまるのだろうとぼんやりと思った。
きみの事を考えていたと言ったら、絳攸はどうするだろう?
きっと目を吊り上げて馬鹿って言って、
そして、明日には忘れてしまうのだろう。
そんなことを考えて返事を出来ずにいると、
それを「きみには話せない」という意味に捉えたのか、
絳攸は「もういい」と言って歩き始めた。
その背中に浮かんだものが、怒りよりも寂しさのような気がして慌てて追いかける。
すると、その足音に気付いた絳攸が振り返って言った。
「いいか、今から私は一人で帰る。
お前と歩いているわけじゃない。
――だから私が何か言っても、それは全部一人ごとだからな」
突然の言葉に訳も分からずただ頷き、
自分よりも歩幅の小さな彼女に追いつかない様に気をつけて歩を進める。
「お前は私の言葉を笑わなかっただろう。
星に手を伸ばすみたいだって言っても。
お前が笑わずに聞いてくれたこと、私は嬉しかった。
お前が覚えていなくても、私は覚えている。
あの時私は思ったんだ。
お前が何かを悩む事があっても、私には何もできないかもしれないけれど、
でも、聞いてやるくらいはできる。
だから、聞いてやるくらいはしようって。
もちろん、お前なら話す相手はいくらでもいるだろうけど。
でも、そんな顔をするくらいなら私にも少し話せよ。
お前のそんな顔を見たら、こっちまで調子が狂う」
絳攸が先を歩いてくれていてよかったと思った。
弛んだ頬を見られたくはない。
あの夜の些細な出来事を、彼女は覚えていたのだ。
喜びで声が震えそうになるのを何とか抑えて漸く、「心強いね」と言ったのに
また「真剣に話しているんだから、真剣に聞け」と怒られた。
ああやっぱりきみは怒っているほうがいい。
そうやって怒ってくれる事がどれだけ私の心を温かくさせるか、
きみは知らないだろうけれど。
冬は嫌いだった。
心の奥にそっと隠しておきたいような醜い気持ちまでも、
白日の下にさらされてしまうような気がして。
だけど、今は、冬も悪くないという気がしている。
冷たい空気はその分だけ、
二人でいる暖かさを教えてくれるように思えるから。
流れる星と絳攸の背中とを交互に見ながら、楸瑛はただ歩くのだった。
【了】

2011/1/3
日記から再掲載です。
双花は冬が似合う気がする。
たぶん、春には春が似合うって言うし、夏には夏が似合うって言うんだけどね。
他の陸軍シリーズと順番に並べるとしたら
流星群前半→陸軍参謀本部の夜→流星群後半→Femme fataleです。
Femme fataleの続きもいずれ。