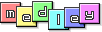日記に掲載していた双花芸能人パロをまとめて再掲です。
双花芸能人パロ設定集
秀麗→諸事情あってマネージャーに。仕事2年目。元気が取り柄だけど、ニブイ
絳攸→人気タレント プロ意識はすごいのですが、onとoffの差が激しい。offではちょっと我儘。そして寂しがり屋さん。
楸瑛→絳攸とユニットを組んでいるタレント。スキャンダル王(笑)。そこも人気。
amayumi:楸瑛と絳攸のユニット名
劉輝→タレント。秀麗が1年目の時に担当していた。スキンシップ過多。ぼんぼん。
燕青→秀麗の先輩マネージャー
静蘭→燕青の担当するタレント
しょうのじーちゃん→↑のすべてが所属するタレント事務所の老獪な社長 元銀幕の大スタア
SHOW-PRO:↑の会社。悪徳プロダクション。
amayumiのCDは通常版のほか、限定版が何枚も出ていて、その違いは封入リーフレット。
二人の密着度に応じてお値段が変わります(笑)
チケットの行方
止まない歓声の中、楸瑛は最後にもう一度だけ振り返り、手を振る。
袖へと下りる階段を、相棒が先に降りていく。
自分の顔がモニターでアップになっていることを確認した楸瑛は
一層沸き上がる会場に応えてキスを飛ばし、自らも絳攸の後を追う。
リハーサルまでは上機嫌だった絳攸が、
コンサート開始直後から急に不機嫌になったことが気になっていた。
いつもにこにことしているようなキャラクターではないから、
そのことを気付いた観客は多くないだろうが…。
客席から見えない場所まで来ると、楸瑛は足早に階段を駆け降りる。
スタッフに声をかけながら、それでも急ぎ足で向かうその先からは、
女性の声が響いてくる。
どうやら一足遅かったようだ。
ようやくたどり着いた楸瑛の目の前には、
相棒である絳攸とそしてマネージャーである秀麗の二人が、
険悪な雰囲気で向かい合っている。
声をかけようとした楸瑛よりも一瞬早く、秀麗が楸瑛を振り返り、
タオルとペットボトルを差し出す。
「お疲れさまでした、楸瑛さん。
明日はオフですけど、しっかり休養も取ってくださいね。
今日は送りはどうしますか?」
にこやかで、それでいて口を挟む余地を与えない言葉。
楸瑛は苦笑いしながらも、答える。
「今日は、送りはいらないよ。
タクシーだけ呼んでもらえるかな?
それより絳攸をあまり責めないでやって…」
「申し訳ありませんが、そういうわけにはいきません。
私はマネージャーとして
最高のパフォーマンスがファンに提供されるようにする責任があります」
きっと眦をつりあげた秀麗を相手に、口応えなどできない。
と、そこに、ぶすくれていた絳攸が割って入る。
「そう思ってるんだったら、なんで客席で見ないんだよ。
一度ファンの熱気も感じたいって先に言ったのはおまえだろう?」
「見てましたよ。ちゃんと後ろから。
絳攸さんの振りがワンテンポ遅れになったのも、
いつもよりキレが無かったのも、
高音の伸びが今一つだったのも、
全部見てたから、こうやって言ってるんじゃないですか!」
「関係者席のチケットはどうしたんだよ。
あそこで見ればよかったじゃないか」
「そ、れは…」
「ちょっと二人とも、そこまで。
秀麗ちゃん、やっぱり送ってくれるかな?
絳攸も、今日はこのまま帰るだろう?」
どんどんと険悪になっていく二人にとうとう楸瑛が割って入った。
会話を途中で止められて、絳攸が一段と不機嫌になったのはわかったが、
あえて気付かぬふりをした楸瑛であった。
気まずい空気。
だれも言葉を発さぬままに、秀麗の運転する車が地下駐車場に滑り込む。
絳攸と楸瑛は、事務所の用意した同じマンションの別の階に
それぞれの部屋を持っている。
そしてなぜか、霄社長の命令で、
秀麗もまたこのマンションの住人となったのだった。
送り迎えがしやすくてその点は便利なのだが、
楸瑛が女性を連れ込むたびに、冷や冷やさせられる。
そういった意味では、家に帰っても気が休まらないのが
唯一の欠点と言えば欠点だった。
しかし、今夜のようにこうも気まずい沈黙が続くとなると、
同じマンションなのも考えものである。
だがエレベーターを降りるまでの辛抱と思い、
二人が乗り込んだことを確認した秀麗が、
自分の居住階のボタンを押そうとした時、
その手を絳攸がつかむ。
「おまえは一回うちにくるんだ」
「ちょ、ちょっと絳攸。女性に手荒なまねはいけないよ」
「お前と一緒にするな。さっきの話の続きをするだけだ」
「だ、そうだけど、秀麗ちゃん大丈夫かな?」
「大丈夫です。私も絳攸さんにお話がありますから」
そう? それならといって、楸瑛はエレベーターを降りる二人を見送る。
絳攸は相変わらず愛想も何もなく、さっさと歩き始める。
(おいおい、キミの部屋は反対方向だよ)
そう思いながら見送る楸瑛が、閉まるドアで見えなくなるまで
秀麗はしっかりと見送ってくれた。
彼女は本当に仕事熱心だ。
自分たちを商品として誇りに思っていて、
その商品価値を高めるために心血を注いでいる。
だから今日のことだって、彼女なりの理由があるに違いないのだ。
絳攸だって、それがわからないわけはないだろうに。
そう思いながらも、思わず頬が緩むのをこらえ切れない。
(あーあ、本当に絳攸はカワイイよな~。
秀麗ちゃんが袖じゃなくて客席で見るからって張り切ってたのに、
蓋を開けてみれば全く知らない人間が座っていたからってあんなに拗ねて。
なにかあったの?って一言聞けばいいのに、それができないんだよねぇ。
好きな子には優しくするのは基本中の基本だよ。
だけど、今のままの方が私は見ていて楽しいからいんだけどね)
そう思いながらも楸瑛はいったん自宅のあるフロアでエレベーターを降りる。
そして携帯電話を取り出すと、
今宵共に夢を見る相手をだれにしようかと考え始めた。

深夜のミルクティー
絳攸は、自分が不機嫌であることを自覚していた。
だけど、それがなぜだかわからない。
半年ほど前から自分と楸瑛のマネージャーに付いている秀麗は、
本当にこの仕事が好きなのだと思う。
みんなに夢を与えるなんてそうそうできることじゃないと、
いつも目を輝かせている。
その分、タレントとしての自分たちを見る目は厳しくて、
時に耳に痛い言葉を遠慮なしに口にすることもある。
けれどそれは全て彼女が自分たちの仕事ぶりを逐一把握しているからであり、
また自分たちを思っての事であることも分かっているから、
絳攸は年下のこのマネージャーを心から信頼しているのだった。
今日だって、彼女の言うことは間違っていない。
客席に目をやって、
彼女のいるはずの席が全く別の人間に占められているのをみて
頭が真っ白になって、ダンスがワンテンポ遅れてしまったのは事実だ。
だけど、彼女はその席で見ると約束したわけで、
それを守らなかった彼女に今日の事を責められるのは
なんだか納得いかなかった。
そんなことを思いながら歩いていると、
後ろから駆け足で近付いてきた秀麗に、袖をつかまれる。
「絳攸さん、共用サロンは気を使うので……」
どうやら自室とは反対方向に進んでしまったらしい。
「わ、分かった。じゃあ、俺の部屋で」
決して間違えたわけではないと心の中で言い訳しながら、
秀麗の後について自室へと向かった。
絳攸の部屋に入ると秀麗はそのままキッチンへと直行する。
絳攸はリビングのソファに腰掛けて、
カウンター越しにその様子を眺めていた。
しばらくすると、ティーカップを二つトレイに載せて
秀麗がリビングへとやってくる。
仕事の後に秀麗はよくこうしてお茶を入れてくれる。
そういう時は、眠りを妨げないようにと、
カフェインを抜いた特殊な茶葉を使って
ミルクティーを入れてくれるのだった。
砂糖を入れなくても程よい甘さのそのお茶を飲んだ日は、
本当にぐっすりと眠ることができて翌日の体も軽いから、
本当は毎日でもここにきてこのお茶を入れてほしい。
茶器も茶葉も全て絳攸の部屋のキッチンに置いてあるのだから、
入れようと思えば自分でも入れられるのだ。
けれど、一度一人で試しに飲んでみたお茶は、
すべてレシピ通りの筈なのになんだか味気なくて、
それ以来やはり秀麗に入れてもらうお茶が一番だと思っている。
なんてことを常春の相棒にちらりとでも漏らそうものなら、
訳知り顔でニヤニヤとしながら、いらぬお節介を焼くに違いない。
だから、普段は楸瑛のいない日だけ
こうして秀麗に仕事後のお茶を入れてもらうことが、
絳攸の密かな楽しみであった。
しかし、いつもは楽しいはずのこの時間が、今日だけは妙に苛立ちを誘う。
そんな絳攸の様子には気付かないのか、
秀麗はいつも通りにまず絳攸の前にカップを置き、
そして自分は床のラグの上に正座をした。
「絳攸さん、ちょっとそこに正座してください」
「……? は? 正座?」
「マネージャーとしてお話があります」
そう真剣な目で言われると、何故だか逆らうことができない。
仕方なく、言われるままに向かい合うように正座する。
すると、両肩にそっと秀麗の手が添えられる。
目の前には、情熱を宿した漆黒の瞳。
化粧気はほとんどないのに瑞々しく艶めく口唇。
肩にあてられた手は、細く小さい。
「絳攸さん……」
「秀麗……?」
だんだんと近づいてくる顔を、
黒くて丸い瞳が可愛いななどと思いながら眺めていた。
なんだか妙に、鼓動が高鳴る。
その、次の瞬間。

彼女のオシゴト
ゴツンという衝撃と共に、目から火花が飛び出る思いがした。
「しゅ、秀麗?」
「痛かったでしょう?でも私も痛かったからおアイコですよ」
「ちょっとまて。なんで俺は頭突きされなきゃいけないんだ?」
その前の瞬間変に高まった俺の鼓動はどうしてくれるのだ、
とはさすがに聞けない。
「私は、確かに絳攸さんとの約束を破りました。
だから、半分は私への罰です。
でも、どういった事情があろうとも、
amayumiは来てくれたオーディエンスに対して
いつものクオリティのパフォーマンスを提供しなければいけません。
それがプロですから。
だから半分は、そうしなかった絳攸さんへの罰です。異論は認めません」
「……、分かった。確かに秀麗の言うとおり、弛んでいた。
それは反省するし、二度と繰り返さない。
だけど、どうして約束を守らなかったのか、
それを聞かせてもらう権利は、あるよな?」
こっちこそ異論を認める気はないと言ってやる。
「……それは、謝ります。申し訳ありません」
「秀麗、謝ってほしいんじゃなくて、理由を知りたいんだ」
「……一人でも、多くのお客様に、かっこいいお二人を見てほしかったから、です」
「どういうことだ?」
「開演前に、ちょっとお客様の様子を見に行ったんですけど……」
約束を違えたそれ自体は悪かったと思っているらしく、
秀麗はぽつりぽつりと事情を話し始める。
開演前に、会場の外の様子が気になって見に行ったのだという。
絳攸と楸瑛が“ルールの守れない人間は嫌い”と公言していることもあって、
amayumiのファンは総じてモラルを持って行動する人が多い。
しかし、一件でも問題があれば、
それがそのままamayumiとしてのイメージ悪化につながることも事実だ。
だから、秀麗はコンサートやイベントのたびに、
会場外の様子をチェックすることを欠かさない。
そして、今日も問題のない事を確認し、会場内に戻ろうとした時に、
泣いている子どもを見つけたのだという。
「小学校1年か2年くらいの女の子だったんですけど、
どうしてもamayumiが見たいって泣いていて。
そばに一緒にいたお母さんに話を聞いたら、
当日券に並んだけど、売り切れてしまったそうで……」
「それで、お前の分のチケットを譲ったのか」
「……、勝手なことをしたのは謝ります。
でも、その子、本当に、絳攸さんと楸瑛さんが大好きなんですよ。
振りまで完璧に覚えてたんです。
TVを録画して毎日見てるって、おかあさんも言っていました。
そんなに夢中になって応援してくれるってすごいことだと思ったんです。
そんなお二人のマネージャーを務めていることが、誇らしいと思いました」
その言葉を聞いて、絳攸は急に恥ずかしくなった。
秀麗が怒ったのも無理はない。
確かに自分は神聖なるステージの上で、集中力を欠いていた。
彼女の誇る商品としての自覚が足りなかった。
「お前は本当に、amayumiが好きなんだな」
ぽつりとこぼれた言葉。
口にしてから、いったい自分は何を言っているのだろうと、思う。
仕事熱心な彼女が“商品”である自分たちを好きでいるのは当然だ。
当然なのに、これではまるで
“商品”としての自分だけに興味を持たれることへの非難の様ではないか。
急いで口元に手をやってみたけれど、一度唇を離れた言葉が戻るわけでもない。
けれど、秀麗はそんなことは気にした様子もなく満面の笑みで答える。
「はい。絳攸さんも楸瑛さんも大好きです。
だってお二人のパフォーマンスは本当にかっこいいんですよ!
お二人とも作品のための努力は惜しまない事を私は知っていますから。
好きにならないはずがありません!」

聞けないキモチ
彼女は仕事の事には厳しいから、これは最高の褒め言葉だ。
それは解っている。
解っているのに、なんだか嬉しくない。
何なんだ、この“自分を見てもらえていない”感覚は……?
そうか、今までは“amayumiの絳攸”の評価しか、聞いていないんだ。
プライベートの俺は、秀麗の目にはどう映っているんだろう?
聞いてみたい。
そう思った衝動そのままに、秀麗に問いかける。
「じゃあ秀麗、amayumiの絳攸じゃない普段の俺は……?」
途中で声がフェードアウトしていったのは、
それを聞いてどうするのだ? という新たな疑問が頭を擡(もた)げたからだ。
“普段の俺の事は好きか?”なんてそんな事を聞いてどうするんだ?
これじゃあまるで、俺が、秀麗の事を好きみたいじゃないか……
「普段の絳攸さんが、どうしたんですか?」
どうやら秀麗には、聞こうとしたことは伝わらなかったようだ。
安堵したような、やはり確かめたかったような、
複雑な気持ちがぐるぐると回っている。
「絳攸さん、どうしたんですか?」
正座して両の拳を膝の上に並べたまま、固まってしまった絳攸を訝しんで、
秀麗が覗き込む。
心配の色を浮かべた上目遣いの視線に捉えられ、ますます絳攸は動けなくなる。
(その目は、反則だ……)
もう何に対しての反則とかそんなことにすら気が回らなくて、
動けないままにだらだらと汗が噴き出してくる。
何故だか頬も、燃えるように熱い。
「絳攸さん、もしかして、熱があるんじゃないですか?」
そう言うと秀麗は予告もなく、額を近づける。
今度は優しく、ゆっくりと。
こつんと触れ合った額は、そこだけでも吸いつくような滑らかな肌だと分かる。
その瞬間絳攸は自分の体温が確実に上がったのを自覚した。
「……、やっぱり、熱い。
絳攸さん、体調が悪いなら、ちゃんと言ってください。
って気付かなかった私は、マネージャー失格ですね」
急にしゅんとする秀麗に、
まさかお前のせいだなどとは言えず、大丈夫だということしかできない。
しかし秀麗は、体調が悪いなら早く休んだ方がいいですと、
絳攸を立ち上がらせ、寝室へと引っ張っていく。
慣れた手つきで、絳攸の着替えを用意すると秀麗は一端部屋を出ていった。
氷嚢を用意してくるつもりらしい。
本当はそんなもの必要ない事はわかっているだけれど、
一生懸命なその姿が可愛らしくて、そのまま見送った。
待っていれば彼女が戻ってくるというのは、悪くない。
そんなことを思いながら、用意されたものに着替え終わり、
ベッドにもぐり込んだ頃に、秀麗が戻ってきた。
「ごめんなさい、絳攸さん。
体調悪いの、マネージャーだったら一番に気がつかないといけないのに…。
すぐに休んでもらわなくちゃいけなかったのに、
あんなに怒ったりしてすみませんでした。」
明日はオフなので、ゆっくり休んでくださいねと言いながら、
そっと額にあてられた手は、
氷嚢を用意したせいでひんやりと冷たく、心地いい。
どうせ熱があると思われているのだからと、
ちょっとした欲望と悪戯心に火がついた。
額にそっと添えられた掌につながる細い手首を捕まえる。
「このままでいて」
「え?」
「気持ちいいから、このままでいて」
「あ、でも、すぐに温くなっちゃいますよ」
「じゃあ、ここにいて」
「いますよ」
「朝までいて」
「そういうわけには……」
「見張ってないと、大人しく寝てなんていられない」
「だめですよ。熱があるんですから」
「うん、だから見張ってて」
「絳攸さんが、こんなに我儘言う人だなんて、知りませんでした」
「うん。我儘なんだ。だから、いて?」
呆れられても構わない。だってこれが本音だから。
もっともっと、本当の俺を知ってほしい。
この気持ちの名前なんて知らない。
判るのは、君の瞳を独占したいということだけ。
【了】

2011/1/3 ブログに掲載していた双花芸能人パロシリーズをまとめて再掲載いたしました。
珍しく楸瑛さんがかっこいいとの感想をいただいた思い出のシリーズです。