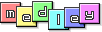LOVE FLIES → SHINE の続きです。

*taste of love*
楸瑛の用意した山のようなノートを驚異的な速さで写し終わると、
少し眠るといって絳攸は眠りに付いた。
どうせ、これで試験だけ受けて、今回もまた主席を取るのだから、
全く絳攸の頭の中はどうなっているのだろうと楸瑛は常々思っている。
その、優秀な頭脳の片隅にでも、自分の居場所は用意されているのだろうか。
一瞬そんなことを思って、すぐに頭を振る。
今彼はここにいる、それだけで十分。
一ヶ月前、手にしながらも全く内容が頭に入らなかった文庫本のページをゆっくりと繰る。
いつもなら読書の供には音楽をかけるのが楸瑛の習慣なのだけれど、
今日はオーディオの電源はオフにしたまま。
眠っている絳攸を気遣ってというよりは、
彼の寝息すらも、聞き逃すのがもったいないとそう思ったのだ。
規則的に上下する夏用の肌掛けを見ているだけで、
なんだか解らないけれど温かくて優しいものがゆっくりと楸瑛の心の中を満たしていく。
ずっとその姿だけを見ていても、多分一生飽きる事など無いと思うと言ったら、
多分絳攸は笑うだろうけど。
少しの名残惜しさと戦いながら、楸瑛はそっとソファから立ち上がった。
背中までの髪を首元で一つにまとめて、楸瑛はシンクに向かう。
しし唐と茄子を素揚げして、
鰹出汁とみりんと薄口醤油をあわせたものに漬け込んで、冷蔵庫で寝かせる。
昆布の出汁も取ってある。
今日は茗荷とわかめと油揚げの味噌汁にしよう。
メバルと長ネギも下ごしらえをして包んであるので、後は蒸すだけだ。
豆の筋を取りながら、
これを茹でてから胡麻と醤油とどちらで和えようか考えていると、絳攸が起き出して来る。
「ごめん、もう少しかかりそうなんだ」
急いで電気ポットにミネラルウォーターを入れながら楸瑛が声を掛けると、
絳攸は瞼を擦りながら頷く。
楸瑛の服を貸しているから、袖が余って、てのひらの中ほどまで覆われている。
「ん、悪い。思ったより、寝ていた」
そう言いながらも、まだ欠伸をしている。
「水飲むかい? 少し待ってくれれば、コーヒーも入れるけど」
ポットのスイッチを入れ、食器棚を開けながら、楸瑛は振り向いて絳攸に問う。
しかし絳攸は返事をする前に、
これで良いと言ってカウンターの上に置かれた楸瑛の飲みかけのグラスに手を伸ばす。
モーゼルクリスタルのグラスの中身は、濃い栗色の液体。
「絳攸それは……」
止めようとしたけれど、間に合わなかった。
予想した通り、絳攸は一口飲んで顔をしかめる。
楸瑛が急いでグラスに水を注いで渡すと、奪うようにして受け取って、
絳攸にしては珍しく、ごくごくと喉を鳴らして飲み干す。
「ごめん、コーラだったんだよ」
「……アイスコーヒーかと思った」
そういいながら絳攸はまだ、顔をしかめている。

後編
養父母(というよりは、彼らに絳攸の養育を任された執事やメイドなのだろうが)のしつけで、
絳攸はジャンクフードを殆ど食べたことが無かったのだそうだ。
コーラも、この独特の味が馴染めないらしい。
インスタントコーヒーも飲まないことは無いけれど、
本当は好きではないのを知っているから、
楸瑛は絳攸と飲むコーヒーはきちんと豆を挽く所から始める。
プジョーのコーヒーミルを回しながら、感触と香りを楽しむのもすっかり習慣になった。
アイスコーヒーだって、きちんとホットの二倍の濃度で入れて冷やすし、
絳攸が来ることが事前にわかっているときには、前日から水だししておく。
食事にしても、絳攸は大体のものは食べるけれど、
本当は出汁の効いた和食が一番好きなのを知っている。
それまで自分が料理をするなんて、考えた事もなかったけれど、
始めてみると、以外に奥が深くて楽しい事を知った。
何よりも、絳攸がその綺麗な箸使いで、残さず食べている姿を見るのが好きだ。
中学高校と六年間バスケット部で鍛えた自分と比べると、
絳攸は小柄で、男性の中では華奢なほうだし、
食自体に執着があるほうではないらしく、
研究に没頭すると、食事を取ることなど頭から抜け落ちてしまう事も多い。
絳攸は知らない。
そんな彼が自分の作った料理を残さず食べてくれる事が、楸瑛をどんなに幸せにしているか。
旬を覚える事も、新鮮な食材の見分けることも、
自分の時間を絳攸の為に使っているという事だけで、楸瑛の心は温かくなるのだ。
30分後。
出来上がった食事を並べ、向かい合ってテーブルに座る。
メバルの身を綺麗に骨から外していく絳攸を見ながら、楸瑛は聞く。
「どうだったのアメリカ(むこう)は?」
「ん、別にどうという事もないな」
なんとも愛想の無い返事に。どうしても聞きたかったことを口にしてみる。
「私が連絡しなかった間、寂しかった? 私が君の事忘れてると思った?」
「別に、寂しくはない」
予想通りの返事に、今更落ち込む事もないと思いながら、しかし、
自分と彼の温度差を感じた楸瑛は空になったグラスに水を入れるために立ち上がり、キッチンへ向かう。
その背中に、絳攸が投げかけた言葉。
「寂しくは無いけど、心配だったな。
お前が連絡してこないなんて、何かあったとしか考えられないだろ。
それに、俺は声など聞かなくてもお前のことを忘れない。
お前だってそうだろう?」
ちょうど背中を向けているところでよかった、と楸瑛は思った。
少しでも緩んだ表情を見られようものなら、
すぐに前言撤回・お前の事など忘れてやると言われかねない。
声が震えてしまわないように、注意しながら漸く、そうだねとだけ答えた。
グラスに水を入れ、再びテーブルに戻った楸瑛に、
茄子の揚げびたしの切り目に箸をいれ、小さく裂きながら、絳攸が言った。
「だけど、お前の飯が食べられないのは、ちょっと寂しかったな。
向こうの日本料理屋は、高いだけで、大して旨くない」
再び頬が緩むのを隠しようも無い。
どうか今だけは、その瞳をこちらに向けないでと思った楸瑛だった。
【了】

あとがき、という名の言い訳
楸瑛さん、うちに嫁に来ませんか?
因みに私は料理が下手なので、この献立おかしいよと思っても突っ込みなしでお願いします。
旬の新鮮な食材を絳攸の為にせっせと手間暇かけて料理する楸瑛さんが書きたかったのです。
乙女楸瑛さん、また書けたら書きたいです。
ちょこちょこと。
たまにはかっこいいところも作ってあげた方がいいのかな?と思いつつも、たぶんうちの楸瑛さんはずっとこんな感じだと思います。
すみません。
タイトルは某バンドの昔の曲から。
楸瑛さんは可愛いですが、元ネタの曲はけっこう怖いです。